洗心言
2009年 盛夏の号
有職のかたち
-

- 有職のかたち【立涌】
- 雲が立ち涌く様子を幾何学的に表わした立涌(たちわく)。運気の高まりを、雲気の上昇に見立てた縁起の良いかたちとして好まれました。
時を超える言の葉
日本の歴史を振り返ると、それぞれの時代に、それぞれの分野で偉業をなした先人たちの至言に出会うことができます。それらは、数百年、千年の時を経たいまも私たちの心に響き、熱く、深く染みわたります。
「時を超える言の葉」。今回は、『枕草子』、『徒然草』と並んで日本三大随筆に数えられる『方丈記』の作者、鴨長明の珠玉の言の葉をご紹介します。
「ゆく河の流れは
絶えずして、
しかももとの水にあらず」
鴨長明
鴨長明(かものちょうめい)は、平安末期から鎌倉初期にかけて生きた人物。賀茂御祖(かもみおや)神社(下鴨神社)の神事をつかさどる家系に生まれた長明は、幼いころより、自分もいつかは宮司になることを望んでいたといいます。その一方で、歌才にたいへん秀でた長明は若くして頭角をあらわし、四十歳代のなかばを迎えるころには藤原定家らとともに、時の権力者である後鳥羽院(ごとばいん)の寵愛を受けるほどの地位を築きます。
ところが、充実した人生を歩んでいた矢先に突然、長明は出家。京の各地を転々としたのちに、法界寺(ほうかいじ)(現在の京都市伏見区に位置)の近くに方丈(約三メートル四方)の草庵を結びます。そして隠遁生活を送るなかでひっそりと、『方丈記』を書き綴りました。
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」は、『方丈記』の書き出しの一節。それは「淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある人と栖と、またかくのごとし」とつづき、大意は「川の流れはとどまることはなく、流れる水はけっして同じではない。水の淀みに浮かぶあぶくは、消えては現れ、また消える。人の世も、同じようなものだ」。
この言の葉が表わすのは、この世に永遠不変なものはないという無常観と厭世観。では、なぜ長明はこのような境地に至ったのでしょうか。その理由は一説に、飢饉や災害がつづく乱世を体験したことや、幼いころからの夢であった神職への道を閉ざされたことにあるのではないかとされています。
繁栄を極めた経済が一気に崩壊し、「百年に一度」といわれる不況が長く、暗い影を落としているこんにち。数多くの人々が、思いがけない変化に翻弄されているいまほど、長明の言の葉が身に迫る時代はないのかもしれません。しかし無常とは、常なることなどひとつもない、ということ。いつまでも雨がつづかないように、沈めば浮き上がるように、いつかかならず、再生の時がやってきます。大事なのは、一時的な混乱に惑わされることなく、自分をしっかりと見つめ直し、自信をもって未来に備えることではないでしょうか。
平安京 今昔めぐり
「平安京今昔めぐり
安楽寿院」
名神高速道路の京都南インターチェンジの南側一帯は、平安時代末期から南北朝時代にかけて、鳥羽離宮が営まれた地。
白河上皇以後、代々の上皇が院政を執り行った離宮の栄華をいまに伝える数少ない歴史遺産が、今回ご紹介する安楽寿院です。
「激動の歴史を生き延びた
天皇家ゆかりの古刹」
平安京の南に位置し、鴨川と桂川とが出会う鳥羽(とば)は古くから、風光明媚な別荘地として貴族たちに好まれたところ。時は十一世紀の終わりごろ、天皇の座を八歳の幼帝、堀河天皇に譲った白河上皇は貴族から献上された地所を大きく広げ、そこに御殿をつくります。これが院御所(いんのごしょ)(上皇の御所)である鳥羽離宮のはじまりです。
その後、院御所は鳥羽上皇に受け継がれ、約百八十万平方メートルにも及んだ敷地には、贅の限りを尽くした壮麗な御殿がつぎつぎに誕生。鳥羽離宮は天皇に代わって政治を行なう院政の舞台になるとともに、苑池では舟遊びが楽しまれるなど、風流な貴族文化の発信地となりました。
安楽寿院(あんらくじゅいん)はそもそも、離宮内に建てられた五つの仏堂のうちのひとつを起源とする寺院。仏堂の創建は保延(ほうえん)三年(一一三七)のことで、本尊には阿弥陀如来像が置かれました。その後、いずれも三重塔の本御塔(ほんみとう)と新御塔(しんみとう)、九躰(くたい)阿弥陀堂などが建立され、寺の規模は大きくなっていきました。
しかし、南北朝時代を迎えると戦火が京を襲い、鳥羽離宮は荒廃。安楽寿院も火災に遭い、さらに地震の被害を受けて仏堂や本御塔、新御塔が失われてしまいました。現在の境内には、新御塔の廃材を用いて慶長年間に建てられたという大師堂や、本尊を安置する阿弥陀堂などが鎮座しています。境内の南側には、豊臣秀頼(とよとみひでより)によって慶長(けいちょう)十一年(一六〇六)に多宝塔様式で再建された新御塔(近衛(このえ)天皇安楽寿院南陵)、同じく西側には幕末に再興された本御塔(鳥羽天皇安楽寿院陵)がひっそりとたたずみます。
ところで鳥羽というと、幕末の戊辰(ぼしん)戦争の発端となった「鳥羽伏見の戦い」でも有名です。安楽寿院には当時、官軍の本営が置かれていましたが、幸いに戦火を被ることなく、こんにちに至っています。
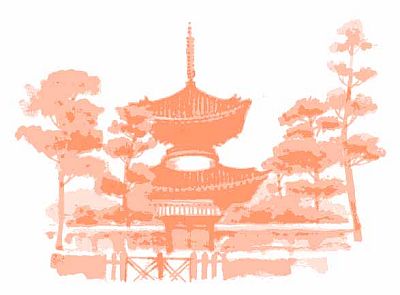
新御塔(近衛天皇安楽寿院南陵)は
唯一の多宝塔様式の天皇陵
百人一首 永久の恋歌
平安人の恋のかたちに心を寄せる「百人一首 永久の恋歌」。
今回は、道因法師の名歌をご紹介します。
思ひわび
さても命は
あるものを
憂きにたへぬは 涙なりけり
- 道因法師
- つれない人を思って悩み悲しんでも、それでも 死にもせず命はあるというのに、涙ばかりは そのつらさに耐えられずにとめどなくこぼれ落ちることです。
胸の奥底に秘めたまま、一生打ち明けることなく終わる恋。平安時代には、そのような「忍ぶ恋」が美しいとされ、和歌の題材としてたいへん好まれました。第八十二番に撰された道因法師(どういんほうし)の一首も、忍ぶ恋の苦しみを切々と詠んだ名歌として知られています。
熱い恋心をあの人はわかってくれない。その無情さは死ぬほど辛いが、どうにかして命はとりとめている。しかし涙はどうしようもない。それは泣くまいと思っていても、はらはらとこぼれ落ちてしまうもの。法師は、「命」と「涙」を対比させることで、恋に苦悩する心境を巧みに詠みあげています。
また、この歌は、どんなに苦しくても、それに堪えて生きていかなければならないとする、法師の人生への思いを表わしたものともいわれています。
道因法師は平安時代末期の人物。俗名を藤原敦頼(ふじわらのあつより)といい、公家としていくつかの役職についた後、八十歳を過ぎて出家したとされています。法師はもとより歌道に熱心な人物でしたが、老齢を迎えたころからますます歌作に打ち込むようになりました。鴨長明の『無名抄(むみょうしょう)』という歌論集には、七十歳を過ぎても「秀歌を詠ませたまえ」と、徒歩で住吉神社に月詣でをしたと書かれています。
法師の死後に編纂された『千載集(せんざいしゅう)』をめぐっては、つぎのような逸話が残されています。『千載集』には当初、法師の歌が十八首入れられていました。ある夜、編者の藤原俊成(ふじわらのしゅんぜい)の夢まくらに法師が現われ、涙を流して礼を述べました。そんな法師をたいそう哀れに思ったのか、俊成は二首を追加して合計二十の歌を選んだというのです。法師の歌作への情熱と執念は、まさに並々ならぬものだったようですね。
小倉山荘 店主より
「緑の田んぼとともに生きる」
夏。田んぼが色鮮やかな緑に染まる時節の到来です。「青田」という季語もあるように、それは日本の夏の盛りを象徴する風景でもあります。しかし今、日本の農山村の原風景が失われかけています。
田んぼは、私たちにとって生命の源であるとともに、多くの生きものたちの棲みかでもあります。鳥たちが羽根を休め、虫たちが元気いっぱいに舞い、水中にはさまざまな種類の小さな生きものたちが暮らす。田んぼは稲を育むだけでなく、一つの生態系を形作っているのです。そして、私たち日本人は稲作を通して自然を慈しみ、その恵みに感謝するこころを育んでまいりました。
食糧や環境問題が深刻化している今、改めて自然を大切にし、そして未来の地球を人類の快適なすみかを、私たちは田んぼを耕すことで考えようとしています。
報恩感謝 主人 山本雄吉

