洗心言
2006年 初秋の号
伝統文様
-
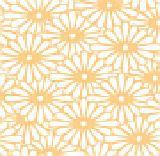
- 伝統文様【菊】
- 秋を象徴し、長寿を願う花として尊ばれてきた菊。九月九日の「重陽(ちょうよう)の節供」は菊の節供とも呼ばれ、平安時代より観菊の宴が行われました。
こころを彩る千年のことば
夏の名残りを癒すそよ風から、冷たい風へ。秋の深まりとともにだんだんと、吹く風が身にしむ時節となりました。この、身にしむという言葉には、秋の冷たさを表わすだけに終わらない、人の深くも優しい思いが息づいています。
珠玉の言葉を昔の歌に訪ね、折々の季節にあわせてご紹介する「こころを彩る 千年のことば」。今回は、「身にしむ」という言葉にこめられた先人の思いを訪ねます。
「人への慈しみの心が
こめられた身にしむ。」
定家の父、俊成が詠み上げた女性の哀れな心情 『小倉百人一首』を編んだ藤原定家の父であり、自らも歌人として名高い藤原俊成の代表作に、つぎの歌があります。
夕されば 野辺の秋風 身にしみて 鶉(うづら)鳴くなり 深草(ふかくさ)の里 大意は、「夕暮れ時が迫ると、野を吹く風に秋の冷気がしみじみと深く感じられることだ。鶉の鳴いている、深草の里よ」。
読むほどに、荒涼とした風景が頭のなかに広がるような一首ですが、しかしこの歌には、単なる叙景歌に終わらない意味がこめられています。
「野とならば鶉となりて鳴きをらん仮にだにやは君は来ざらむ」という、『伊勢物語』に詠まれた歌を本歌として、鶉には「憂(う)」と「辛(つら)」をかけ、男を待ち続けるあまり、鶉に変わり果てた女性の哀れな心情がつづられているのです。
「染みこむ水のように、
沁み渡る痛みのように」
この歌で、重要な役割を果たしているのが「身にしむ」という言葉です。
その意味は、「しみじみと深く感じ入る」。
「しむ」は漢字で表わすと、「染む」、または「沁む」となります。
ふたつの漢字の意味を考えたうえで「身にしむ」の意味をさらに辿ると、この言葉には、寂しさや侘びしさをあたかも乾いた身体に染みこむ水のごとく、あるいは五体に沁み渡る痛みとして受け止めようとする心が、こめられているように思えます。
そして、その心をつぶさに見つめると、自らの悲しさだけでなく、人の辛さまでも我が苦しみとして受け入れようとする心、すなわち慈しみの心が優しく息づいているように感じられてなりません。
「多くの嬉しさや喜びが
「身にしむ」世の中へ」
現実よりも仮想の世界に関心が注がれ、人と人とのつながりが希薄となり、誰もが他者の痛みを忘れがちな昨今の社会。
だからこそ、先人が「身にしむ」という言葉に託した心の大切さを、いま一度じっくり噛み締めたいと思います。
もちろん、私たちが「身にしむ」のは、痛みや辛さだけではありません。
嬉しさや喜びもそうであることは、皆さんもよくご存知のことでしょう。
幸せが「身にしむ」世の中が訪れるように。
一人ひとりの小さな願いが、やがて大きな実を結ぶことを、いつまでも忘れたくないものです。
平安のまつり
「平安の祭
鞍馬の火祭」
「サイレイ、サイリョウ!」の掛け声とともに、燃え盛る大松明を担いだ男衆が街道を練り歩く鞍馬の火祭。
秋の気配漂う山あいの郷を火の粉でつつむ勇壮な神事は、今宮神社のやすらい祭、広隆寺の牛祭とともに、京都三大奇祭に数えられています。
「百数十本の大松明が
乱舞する炎の饗宴」
牛若丸(源義経)ゆかりの地として、あるいは天狗伝説で名高い鞍馬は、京都市北部の山あいの地。火祭は、山の中腹に鎮座する鞍馬寺の鎮守の杜、由岐(ゆき)神社の例祭として、毎年十月二十二日に行われます。
その起源は、平将門の乱や大地震などが相次いだ平安時代中期の天慶(てんぎょう)三年(九四〇)。世の中を平定するため、朱雀天皇が由岐神社を御所から鞍馬寺に遷す際に繰り広げられた松明(たいまつ)行列が、ルーツとされています。
午後六時、「神事に参らっしゃれ」の合図により、鞍馬街道沿いの家々の軒先にエジ(篝火(かがりび))が灯されると、祭のはじまりです。最初に、トックリと呼ばれる小さな松明を手にした着物姿の子どもたちが練り歩き、小・中学生の行列がそれに続きます。
そして、いよいよ大松明の登場です。黒の締め込みに化粧回しをつけ、脚絆(きゃはん)、黒足袋、武者草鞋(むしゃわらじ)姿の男衆が四、五人がかりで担ぐ松明の大きさは、長さ約四メートル、直径は一メートル近く、重さは百キロ以上。「ドンコ、ドンコ、ドコ、ドコ、ドン」と鞍馬太鼓が打ち鳴らされ、「サイレイ、サイリョウ」の掛け声が響く街道に、燃え盛る大松明が次から次へと現われると、あたりは見ているだけで火傷しそうな熱気と煙りにつつまれます。
午後九時過ぎ、鞍馬寺の仁王門前に百数十本の松明が火の粉を飛ばしながらひしめき合い、炎の饗宴は最高潮に。注連縄が切られるやいなや、男衆は石段を一斉に駆け上がり、やがて二基の神輿が火の粉舞うなかを豪快に降りてきます。
それぞれの神輿の担い棒には、逆さ大の字形にぶら下がる二人の若者。これはチョッペンの儀といわれ、鞍馬の地に伝わる成人式なのだとか。神輿はその後、男衆に担がれて街道を巡行した後、夜中の十二時を過ぎてようやくすべての儀式が終了します。
祭の模様は、志賀直哉の代表作『暗夜行路』にも詳細に記され、実際に祭見物に繰り出す前に一読するのも一興です。

名歌故地探訪
『小倉百人一首』に撰された歌にゆかりの深い地をご紹介する「名歌故地探訪」。
今回は京都、相楽を訪ねました。
来ぬ人を
まつほの浦の
夕なぎに
焼くや藻塩の
身もこがれつつ
- 権中納言定家
- いくら待っても来ない恋人を待っている私。風の止む 夕凪時に焼く松帆の浦の藻塩草のように、身も心も恋い焦がれています。
歌に詠まれた松帆の浦は、こんにちでは松帆崎といい、淡路島の最北端に位置する岬。目の前には、海の青と白波のコントラストが美しい、明石海峡がパノラマのように広がります。松帆の浦の名はあたりを松林が覆うことに由来し、風光明媚な景勝地として古くより知られていました。松帆の浦はまた、舟の航行のための潮待ち、風待ちの地としても名を馳せたところ。一説に、松帆は「待ち帆」が転化したものともいわれています。
現在、松帆の浦の近くには世界最長の吊り橋である明石海峡大橋が架かり、宿泊施設などが整備され、多くの行楽客が訪れる観光地となっています。
藻塩(もしお)は、縄文時代から伝わる製法でつくられた塩のこと。天日干しした海藻を簀の上に積み、海水を幾度も掛けて塩分を多く含ませ、これを焼いて水に溶かし、その上澄みを煮詰めて塩を採りました。
作者の権中納言定家(ごんちゅうなごんさだいえ)は、『小倉百人一首』の撰者である藤原定家その人。権中納言は、定家が昇りつめた最終官位のことです。
来ぬ人を待つ女心のもどかしさ、じりじりと思い焦がれる気持ちをさまざまな比喩表現を用いて詠みあげたこの歌は、定家の円熟期の五十五歳のときのもの。定家は、この歌のように叙情的な作品を得意としましたが、それは父の藤原俊成が唱えた「幽玄」をさらに進化させ、「有心(うしん)」という独自の美的理念を確立した故のことでした。
ところで、定家の性格は内向的なうえにたいへん偏屈だったそうで、恋愛経験もほとんどなかったのだとか。そんな人物が、不朽の名作と呼ぶにふさわしい恋の歌を詠むあたり、その想像力の奥深さは、きっと計り知れないものだったのでしょう。
小倉山荘 店主より
諌(かん)言は耳に痛く、良薬は口に苦し 「孔子」
儒教の祖である古代中国は春秋時代の大思想家、孔子の言葉です。 人からの忠言や諌(いさ)めの言葉を聞くのは辛いものですが、自分のためには優れた効き目があることの喩えです。
人は得てして、成功体験を繰り返すうちに自らの力を過信し、いつしか傲慢な気持ちが心に芽生え、他人の意見に耳を貸さない独善的な態度に陥りがちです。その結果、足下が揺らぎはじめても気づくことなく、手後れになってしまいます。
「山中の賊を破るは易し、心中の賊を破るは難し」。
この中国の諺は、敵を打破することは容易(たやす)いが、自らの心を律することの難しさを説いています。
たとえ耳に痛くとも厭うことなく、安泰で順調なときにこそ忠言や諌めの言葉を良薬とする謙虚な姿勢や心を養っていきたいものです。
報恩感謝 主人 山本雄吉

