洗心言
2019年 初春の号
四季折々

- 色づく心 梅
- 寒さに耐え、どの花よりも早く咲くことから百花の魁と呼ばれた梅。艶やかな姿と馥郁たる香りは、縁起物として人々に愛されました。
今を生きるやおよろずの魂
「八百万の神」というように、あらゆるものに人智を超えた力が宿ると考え、それらを畏れ敬ってきた私たち日本人。
永き時を超えて、今もこの国に生きる「やおよろずの魂」をご紹介します。
年の初めに、家に幸せをもたらす年神
お正月といえば、一年のうちで最もおめでたいときです。みんな口々に「あけましておめでとう」というお正月ですが、なぜめでたいのか。その理由をあらためて訊ねられると、うまく説明できないという人も多いのではないでしょうか。
もちろん新しい一年が始まるのは、それだけで喜ばしいことです。しかしお正月がめでたいのには、それだけに終わらない、この国ならではの理由があります。
日本では古くから、お正月は年神を迎えるときと考えられてきました。
年神とは、訪れた家にその年の幸福や健康をもたらす神のこと。つまり、お正月がめでたいその理由は、年神が家にやってくることにあるのです。
年神の正体については、さまざまな説があります。たとえば、穀物の神という説。日本で米づくりが広まると稲作が暮らしの中心となり、人々は稲を育てる神を崇めるようになりました。それが年神であり、先人たちがお正月に年神を家に迎えて手厚くもてなしたのは、その年の豊作を祈願するためだったと考えられています。一説に、「とし」は本来穀物の実りを表す言葉であり、収穫に一年を要することから「年」の意味になったとされています。
年神を祖霊神、つまり先祖の霊と考える説もあります。ちなみに祖霊神は、ふだんは山の神として山から子孫たちを見守り、春になると田の神となって里に降りてきて稲の成長を見守り、収穫が無事に終わるとふたたび山に戻ると考えられていました。
はっきりした正体は分からないものの、先人たちはお正月を、年神を迎えるためのものとして大切にしてきました。年末の大掃除に始まり、お正月に関するほとんどの行事が年神をもてなすために行われ、たとえば門松は年神を家に迎えるための目印であり、鏡餅やおせち料理は年神への供え物であったといわれています。
ところで年神は歳徳神とも呼ばれ、こちらは節分の主役。歳徳神は恵方にいるといい、恵方を向いて無言で巻き寿司を食べると縁起が良いとされることを、皆さまもよくご存知のとおりでしょう。
ことし一年をより良い年とするためにも、年神にもっと関心を寄せてみてはいかがでしょうか。
京都のまるまるさん
京都にむかしからある、いろいろな「さん」付けの言葉のなかからいまもよく見かけたり、耳にすることの多いものやことをご紹介する「京都のまるまるさん」。
初春は、おあげさんについてのお話しです。
京都の料理に欠かせない、おあげさん
宮中で使われた御所ことばの名残か、丁寧なもの言いが特徴とされる京都の言葉。それは食べ物にもあてはまり、京都の人は口に入れるものまで、まるで人を呼ぶかのように「さん」を付けて丁重に扱ってきました。
食べ物を大切なものと考えているから、あるいは、目上の人に差し出すものだったから。その理由には諸説ありますが、ともあれいまも京都では、お豆さんやお粥さんのように食べ物にさんを付けることがあり、「おあげさん」もその一つ。おあげさんとは豆腐を油で揚げた油揚げのことで、そもそも精進料理の素材として発達した食べ物です。
京都には、おあげさんを使ったさまざまな料理があります。おばんざいとして知られているのが「たいたん」。これは「炊いたもの」が変化した言葉で、多くは油揚げと大根や小松菜、かぼちゃなどの野菜を一緒に煮たものを指します。この、甘辛く煮たおあげさんの中にすし飯をつめれば、伏見稲荷大社ゆかりの「おいなりさん」、つまり、いなり寿司に早変わり。また、このおあげさんと青ねぎを卵でとじ、ご飯にのせると「衣笠丼」のできあがり。これはその姿が、金閣寺の近くにある宇多天皇ゆかりの衣笠山に似ていることから名付けられた、京都発祥のメニューといわれています。
このほかにも、おあげさんを使った料理はたくさんありますが、変りだねは京風の「たぬきうどん」。これは餡でとろみをつけたきつねうどんに、おろしショウガを添えたもの。なぜ、きつねがたぬきになったのかよく分からないそうですが、あつあつのうどんは底冷えの京都にぴったりです。
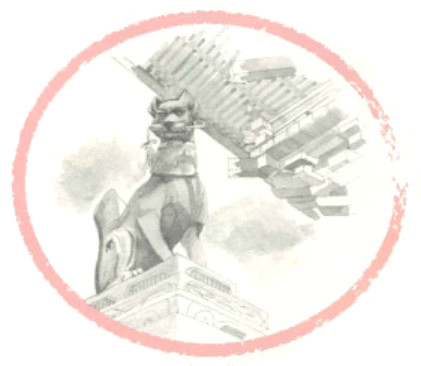
『小倉百人一首』を生んだ藤原定家
鎌倉時代を代表する歌人であり、『小倉百人一首』を編んだ藤原定家。その生き様はどのようなものだったのでしょうか。
藤原定家は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて生きた人。歌壇の重鎮であった父、藤原俊成の教えを受けて幼いころから類いまれなる歌才を現し、治承二年(一一七八)に若干十七歳で初めて歌合に参加しました。その二年後に源平合戦と呼ばれる治承・寿永の乱が始まり、定家は激動の世を歌人として生きるにあたっての心構えを、日記『明月記』に次のように記しました。
「紅旗征戎吾ガ事ニ非ズ(たとえ大義名分のある戦であろうとも、芸術を職業とする自分には関係のないことだ)。」
五摂家の一つである九条家に仕えながら、和歌の道にますます精進した定家は西行などとの交流を通して、歌壇に新風を巻き起こします。そのころに詠まれた歌の一つが、こちらです。
見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮
あたりを見渡すと、花も紅葉もない。海辺の漁師小屋があるだけの秋の夕暮よ。
本歌取りの技法などに凝り、風雅な情趣を余情のある表現によって詠み、華やかさを求めた定家の歌は難解とされ、旧風の歌人たちから禅問答のようだと揶揄されることも少なくありませんでした。また、九条家の衰退もあり、暮らし向きも悪くなっていました。
しかし困難に屈することなく、旺盛に歌を詠み続けた定家は後鳥羽院に見出され、『新古今和歌集』の撰者という名誉を与えられます。そして、歌壇の中心人物となった定家は創作とともに歌の評論に力を注ぎ、後堀河天皇の時代には『新勅撰和歌集』の編纂を手がけました。
『明月記』によると、『小倉百人一首』の原点である『小倉山荘色紙和歌』が成立したのは、晩年の文暦二年(一二三五)。百歌を選りすぐることは、歌を愛した定家にとって、人生の仕上げだったのかもしれません。
小倉山荘 店主より
めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな 紫式部
月がひときわ美しく見える時節、風流を好んだ平安人であれば、月の出が待ち遠しくて仕方がなかったことでしょう。はやる気持ちを抑えて夜を待ち、やっと月を見つけたと思ったらすぐに雲隠れされてしまった。
もっとも、紫式部が感じた悔しさの理由はほかにありました。その夜、紫式部のところに友人がやってきました。しかし、月を眺めながら語り明かそうと、ずっと待ち続けた紫式部の気持ちを知ってか知らでか、待ち人はすぐに帰ってしまったのです。あたかも雲隠れする月と競争するかのように。
私たちの人生は、あらゆることを「待つ」ことで成り立っているように思えるのです。誕生日を待つ、良い知らせを待つ、お正月を待つ。なかでも私たちが生涯にわたって待ち続けるもの、それは紫式部の歌にあるように、人であり、人の思いやりであり、人の心の交わりを知らず知らずのうちに、私たちは待ち続けているのではないでしょうか。
雲がくれにし 夜半の月・・・になるのではなく、お互いが待つ人の心に応え合っていく。そこに人生を幸福にし、豊かにする秘訣があるのだと思います。
報恩感謝 主人 山本雄吉
追伸
今号をもちまして『洗心言』の発行を終了させていただきます。
平成十四年の創刊以来、十八年の長きにわたりご愛読いただき誠にありがとうございました。
この三月からは、新たに皆さまと私どもを結ぶ小冊子を通してお目にかかります。
引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
再拝
